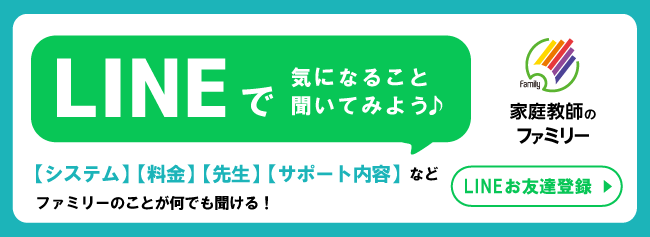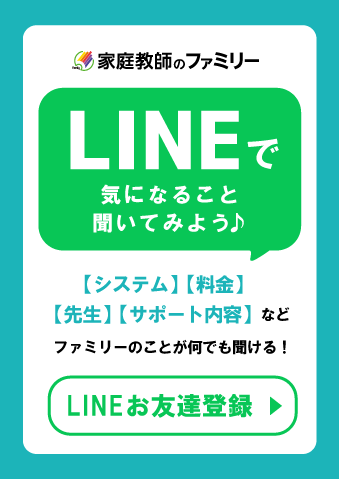勉強習慣の付け方は?子どもと言い争いにならずに習慣を付ける方法コツ

2023.07.13
ファミリー 代表 寺井俊行
こんにちは!家庭教師のファミリーです。
子どもの成績を伸ばすには、勉強習慣を身に付けさせることが大切です。
勉強習慣が身に付けば、子どもは積極的に勉強に取り組むようになります。
勉強がわかるようになることで、自分に自信を持てるようになる子も多いでしょう。
では、どうすれば子どもに勉強習慣を付けさせることができるのでしょうか。
今回は、子どもの勉強習慣の付け方について詳しくご紹介します。
勉強習慣の付け方で悩む親が多い
「子どもが全然勉強しない」「テスト前に一夜漬けの勉強しかしないので成績が上がらない」など、子どもに勉強の習慣がなく、困っている保護者さまは少なくありません。
なかには「つい勉強しなさいと声をかけて子どもと喧嘩になってしまう」という方もいるのではないでしょうか。
このように子どもに勉強の習慣が付いていない場合、その原因は「勉強の正しい仕方、習慣の付け方がわかっていない」ことにある可能性が高いです。
また、ゲームやスマホなどの使用に決まり事がなかったり、生活が不規則であったり、親が勉強嫌いで子どもに伝播していたり、コミュニケーションが少ないなど、親や家庭環境が原因で勉強へのやる気が削がれているケースもあります。
勉強の正しい仕方・習慣の付け方を知ること、そして親の意識を変えて行くことも重要です。
勉強をするために整った環境があること、自分に自信を持つことは、勉強へのやる気に繋がります。
勉強習慣がないとなぜ困る?
勉強習慣がない子どもは、次のような点で壁に直面する可能性があります。
- ・授業についていけない
- ・やる気や自信が低下する
- ・将来の選択肢が狭くなる
勉強習慣がない子どもは、学校の授業についていけなくなり、先生から注意を受けることも増えます。
これにより、やる気や自信をなくし、さらに勉強についていけなくなる悪循環に陥る子もいるでしょう。
勉強がわからないままだと、行きたい高校や大学に行けず、将来の選択肢は狭まってしまいます。
将来やりたいことをやるためにも、勉強の習慣付けは大変重要といえるでしょう。
プロ教師が直伝!勉強の習慣の付け方で失敗しないコツとは?

失敗せずに勉強習慣を身につける4つのコツ
- まずは習慣化(ルーティン)することを最優先に※スモールステップ(一日15分など)
- 予定を立てる(スケジュール表の作成)
- カレンダーに記録する(家族に公表する)
- 完璧を目指さない(三日坊主は当たり前)
コツ1:まずは習慣化(ルーティン)することを最優先に
勉強習慣とは、勉強をするという行動習慣ということになります。
今まで勉強習慣がない子どもの場合、いきなり勉強習慣を身につけることはかなりハードルが高いので、まずは勉強の中身よりも決まった時間になったら「勉強する態勢をとる」ということを習慣化させましょう。
ポイントは毎日、継続的に続けることにありますので、初期段階ではとにかく続けることに重点を置いて取り組みましょう。
最初から欲張って高望みをするのは厳禁です。
これだったら絶対にできるという内容で始め、スモールステップを重ねるのもポイント。
例えば、1日1時間勉強するという高い目標ではなく、初期段階は1日15分または20分から始めます。
たったの15分と思われるかもしれませんが、大事なのは1日15分でも続けることですので、あせらずに行きましょう。
続けているうちに15分では物足りないということであれば、15分または20分を1セットとして、時には2セットやっても構いませんが、最低1セットを実施できたらOKとしましょう。
初期段階では時間の長さでも内容でも中身でなく、継続することだけに集中を。
「1日15分を毎日継続できた」という成功体験を作ってあげることが、その後に大きな自信となります。
行動が習慣化するには最低でも1ヵ月はかかると言われています。
最初の1ヵ月目は長さや内容にこだわらず、15分を毎日続けましょう。
そして1ヵ月間続けることができたら、2ヵ月目からは2セット(30分または40分)というように少しずつ時間を増やします。
決して欲張らずに、ゆっくりと期間をかけて少しずつ増やすことがコツです。
とにかく継続することが最も大事だということを忘れないでください。
コツ2:予定を立てる(スケジュール表の作成)
1日15分(20分)と決めても、好きな時に自由にやるというよりは、やる時間帯を毎日決めておくと習慣化しやすいと言われています。
そのために毎週の曜日ごとに勉強する時間をあらかじめ決めます。
例えば、月曜日から金曜日までは18時スタート、土日は17時スタート(日曜日は休んでもよい)というように、時間帯を決めるときも子ども自身が自分で決めます。
なるべく他の予定が入らない時間帯を選ぶとよいでしょう。
この時に、勉強以外の予定(食事やお風呂、ゲームなど)も曜日ごとに決めてしまう方もいますが、あえて他の予定は決めずに勉強時間だけを決めるのがポイントです。
すべてを計画通り、予定通りに進めたい方もいますが、勉強習慣がついていない子どもはもともと計画通りに行動することが苦手な場合が多いため、勉強以外のことであっても計画通りにできないことが続くと「できない」経験を積み上げてしまうことになりますのでおすすめしません。
今回の目的は勉強習慣を身につける(継続する)ということですから、予定を決めるのは勉強時間だけでかまいません。まずは勉強する時間だけを決めましょう。
勉強する時間・スケジュールが決まったら、カレンダーに書き込んだり、スマホに入力するなどして記録します。
予定をスマホに入れてアラームがなるようにセットすれば、勉強する合図にもなるので効果的。
ポイントは決めた予定を常に見えるようにすることです。
コツ3:カレンダーに記録する(家族に公表する)
勉強する予定を書くだけで終わりではありません。次に大事なことは、予定通りに実行できたら、それを記録することです。
できれば1ヵ月や3ヵ月が一目でわかるカレンダーに、実行できたら〇印や☆印など自分の好きな印をつけます。
15分を2セットしたら〇〇や☆☆とつけてもよいでしょう。
とにかく、実行できたという結果を記録に残してあとで振り返られるようにします。
また、そのカレンダーは家族にも見えるように廊下やリビングなどに貼るようにしましょう。
自分で決めたことを家族に公表するということもモチベーションの維持に役立ちます。
親としては、どうしてもテストの点数や成績といったことに目が行きがちになりますが、勉強習慣をつけさせたいとお考えでしたら、勉強した内容やテスト結果は一度棚上げして、毎日コツコツと勉強しているという行動(習慣化)に目を向けてあげましょう。
そして、子どもの頑張りを見て声をかけたり、褒めてあげたりしてください。
子どもにとって、親からがんばりを褒められることが何より力になります。
大変だけど続けようという、やる気につながるのです。
コツ4:完璧を目指さない(三日坊主は当たり前)
勉強習慣が身についてしまえば後は楽ですが、実際には習慣化できずに挫折してしまう子どもが大勢います。
勉強さえすれば、もっとよい成績が取れるのに、もったいないという親御さんの気持ちはよくわかります。
それだけ勉強の習慣化は非常に重要なことなのです。
そこで、途中で挫折することなく勉強習慣を身につけてもらうためには、完璧を求めないということがポイントです。
何事もそうですが、続ける、継続するためには忍耐力が必要になります。
「三日坊主」という言葉をご存じの方も多いと思いますが、3日も続けられないほどのダメな人とネガティブなイメージで使われることが一般的ではないでしょうか。
このネガティブなイメージが習慣化を邪魔することになるのです。
自分は、たった3日ですら続けられないダメなひとなんだと勝手にマイナスイメージを自分に与えてしまうことにつながります。
そうして継続してできないことが続くと、今度は三日坊主とバカにされたくないために、三日坊主とバカにされるくらいなら、そもそも勉強なんか初めからやらないと自分に誓うことになってしまうのです。
勉強習慣をつけるといってやり始めたことが、いつの間にか勉強なんか絶対にやらないというように変わってしまっては本末転倒です。
そうならないためには、「三日坊主はダメなことじゃない」と認識を改めましょう。
むしろ、逆に「三日坊主は当たり前」と3日続かないことはよくある当たり前のことで決してダメなことではないんだと認識をポジティブに変えることが大事。
その上で、最初から完璧にできる人なんていないんだと言い聞かせて、根詰めずに、ゆるい感じで始めることを心がけてみましょう。
続かない日があっても、まったく問題ありません。
三日坊主を毎回繰り返したら、それはそれでもう立派な継続と言えますし、勉強習慣が身に付いたと言ってもいいのです。
3日に1回休んでもまったく問題ないのです。
勉強習慣とは1回も休まない、サボらないということではなく、1回休んでも継続して勉強している状態のことを言いますのでよく覚えておきましょう。
勉強へのモチベーションの上げ方については、以下のコラムでご紹介しています。
勉強のモチベーションの上げ方は?下がる原因や理想的な環境についても解説
勉強を習慣化させるのにNGなこととは?失敗するダメな例
勉強を習慣化させるためには、次のような勉強の仕方は避けるようにしましょう。
- ・勉強のハードルを上げすぎる
- ・睡眠時間を削る
- ・気が散る環境で勉強する
- ・「勉強しなさい!」の声かけ
お伝えしたように、勉強のハードルを上げすぎてしまうと、毎日勉強することが子どもにとって負担になり、勉強は続きません。
また、睡眠時間を削って勉強するのもNG。
睡眠が足りていない状態では、うまく頭が働かず、勉強の効率は落ちてしまうでしょう。
これは、気が散る環境下での勉強も同様です。
スマホやゲームが近くにあったり、テレビがついていたりする場所では、子どもは勉強に集中できません。
勉強習慣を身に付けるためには、まず勉強に集中できる環境を整えてあげることから始めるといいでしょう。
もうひとつ、気をつけておきたいのが「勉強しなさい!」の声かけ。
つい強い口調で勉強するよう子どもに命令してしまう方は多いでしょう。
しかし、この声かけは子どものやる気を削いでしまいます。
子どもに勉強させたいときには、叱るのではなく、まずは勉強する環境作りが先ですので、先ほどからお伝えしているように勉強の習慣化に向けた取り組みを実践しましょう。
勉強習慣を身に付けさせるには第三者の協力が必要なことも!
勉強習慣を身に付けさせようと親が工夫をしても、つい感情的になってしまったり、子どもが反発したり、やる気を出してくれなかったりしてうまくいかないケースは珍しくありません。
そのような場合には、家庭教師など、第三者による協力を仰ぐのもひとつの方法です。
家庭教師のファミリーでは、勉強習慣がない子ども達に対して以下の手順で実際にトレーニングしていますので簡単にご紹介します。
SETP1:ルール作り
- いつ勉強するのか(勉強する時間帯を決める)
- どこで勉強するのか(勉強する場所を決める)
- 何を勉強するのか(勉強時間中にやる内容を決める)
- どれくらい勉強するのか(勉強する時間数や量を決める)
STEP2:家族に宣言
スケジュール表を作り、これからやることをみんなに宣言する。
STEP3:記録
カレンダーに勉強した日を記録する。
家庭教師のファミリーでは、小学校1年生から高校3年生まで幅広く勉強や成績・受験などで悩みを抱えている子ども達に対してマンツーマンで対応し、ティーチングとコーチングを掛け合わせた独自メソッドで、子ども達の自立学習をサポートしています。
お子さま一人ひとりの特性を理解した上で考えられた、ピッタリの学習対策で成績を伸ばすだけでなく、自分から勉強する習慣を育てています。
ご家庭での勉強の習慣付けがうまくいかないという方は、ぜひ一度家庭教師のファミリーの無料相談をご活用ください!
勉強習慣の付け方を実践して「主体性を持って勉強する子」に
子どもにやる気と自信を持たせ、将来の可能性を広げてあげるために、早くから勉強習慣を身につけることは非常に重要です。
しかし、子どもになかなか勉強習慣が身につかず、悩む保護者さまは少なくありません。
勉強習慣が身につかないのは、勉強の仕方がわからないことが根本原因であることが多いです。
①スモールステップで続けることを最優先、②スケジュール表を作って予定を決める、③家族に公表してカレンダーに記録する、④完璧を目指さずにゆるい感じで気楽に取り組むといった勉強習慣を身につけるコツを実践すれば、いちいち親に言われなくても主体性をもって勉強に取り組む子どもに成長するでしょう。
また、子どもの勉強にあたっては、環境を整えてあげることも大切です。
親御さまによる「勉強しなさい」という言葉は子どものやる気を削いでしまうので、言わないよう注意しましょう。
それでも勉強習慣が身に付かないという場合には、家庭教師のファミリーにご相談ください。
家庭教師のファミリーは、膨大なデータと心理学にもとづいたメソッドによって、子ども達の自立学習をサポートします。
まずは資料請求や無料体験をお気軽にご活用ください。
著者ファミリー 代表 寺井俊行

大学生の家庭教師が主流の中、顧客からのより専門的で高度な要求に応えるため、教師のプロフェッショナルとして、質の高い授業を提供。
常にハイレベルな授業を提供できるように、日々指導法や教材の研究等を行い、また、大学生や一般の家庭教師に対して研修や授業のアドバイスを行うことで、ファミリー全体の授業スキルの向上を図っています。
お電話でのお問合せ
フリーダイヤル

14:00〜21:00
(日祝休み)
- 教育情報コラム
- 先輩たちの成功体験談
- ファミリーの賢い利用法
- 勉強お役立ち資料
お電話でのお問合せ
フリーダイヤル

14:00〜21:00
(日祝休み)