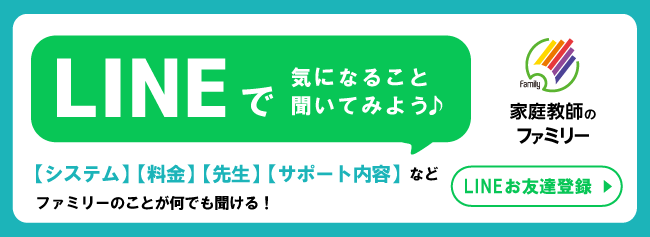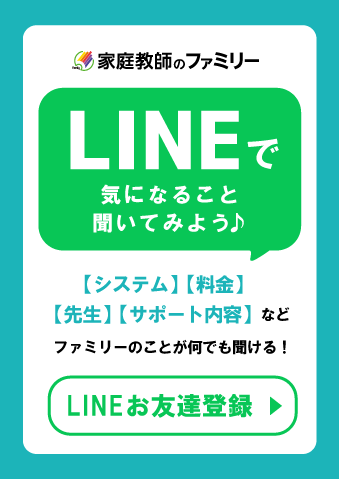認知能力・非認知能力とは?今後の教育で非認知能力がますます重要に!

2024.06.14
ファミリー 代表 寺井俊行
こんにちは!家庭教師のファミリーです。
これまで、子どもの教育においては学力や偏差値のような「認知能力」の向上が重視されてきました。
しかし、近年では「非認知能力」が注目され、それを身に付けるための取り組みを行う家庭が増えています。
では、この認知能力・非認知能力とはどのようなものなのでしょうか。
今回は認知能力・非認知能力の概要と、非認知能力を身に付ける重要性・方法についてわかりやすく解説します。
認知能力・非認知能力とは?簡単にわかりやすく解説
まずは、認知能力・非認知能力がそれぞれどのようなものなのかご説明します。
認知能力とは
認知能力とは、数値化できる知的能力のことを指します。
例えば、学校や塾で行われる学力テストの点数や知能指数を表すIQなど。
このような具体的な数値で表される能力が、認知能力です。
認知能力を高めるために多くの家庭では、学校以外に学習塾・個別指導塾・家庭教師・通信添削・デジタル教材など様々な学習機会を子どもに与え、また多くの時間と教育費を費やしています。
しかし近年では、高学歴難民という言葉でも表現されているように学力や学歴が高いからといって必ずしも希望する職につけるとは限らず、非正規労働者となったり無職のまま心身を病んでしまったりという若者も目立つようになってきました。
そうしたことから将来、子どもに幸せな人生を送らせるためには学力や偏差値といった認知能力の向上だけでは不十分であることが指摘されており、認知能力と対を成す「非認知能力」の育成と向上が大人になるまでの教育期間において注目されるようになりました。
非認知能力という言葉は、あまり聞きなれない言葉だと思いますが、自己肯定感という言葉と同様に、自分の人生を自分の足で歩んで行くために欠かせないキーワードです。
ご存じない方は、ぜひともこの機会に理解を深めていただき、お子様の未来教育に活かしていただきたいと思います。
非認知能力とは
非認知能力とは、認知能力のように数値では表すことができない内面的な能力のことを指します。
例えば、次のような力が非認知能力にあたります。
- ・自己肯定感・自信
- ・主体性・意欲
- ・物事をやり抜く力
- ・創造性
- ・好奇心
- ・自制心(セルフコントロール)・忍耐力
- ・想像力
- ・共感力
- ・コミュニケーション力
- ・社会性
これらの力は、テストやIQのように数字で表すことはできませんが、「ある・ない」とか、「高い・低い」とか、「強い・弱い」という表現で評価することができます。
認知能力と非認知能力の区別は、「数値化できるか、できないか」でお考えいただくと区別しやすいと思います。
また、認知能力が【学力的・知識的】であるのに対し、非認知能力は【思い・考え・気持ちが伴う内面的】なものであるという点も、大きな違いでしょう。
非認知能力は、社会に出て人と関わり、心身ともに充実した豊かな人生を生きていくにあたって欠かせないものです。
例えば自己管理能力・実行力・探求心は周りから評価されたり、出世したり、自己実現の達成のために深く関わっています。
人にわかりやすく伝えたり、共感をしたり、支持を得られる提案をするなど、コミュニケーション能力も世の中や人間社会において非常に重要です。
実際に、非認知能力の高さが人生の充実につながるという研究結果も報告されていることから、近年では非認知能力の重要性が広く認められるようになり、それと呼応するように子どもの非認知能力教育に力を入れる例が増えてきています。
また、自ら疑問を持って探求する力がつくと、思考力や物ごとの本質を考える力が高まって地頭が鍛えられるとともに、勉強の効率も上がるため、知識の詰め込みだけでは通用しなくなった今の入試傾向にも自然と役立つことは言うまでもありません。
非認知能力はなぜ今後ますます重要になってくるのか?

非認知能力が重要視されてきていることをお伝えしましたが、保護者世代だけでなく企業も含めた社会全体で今後ますます注目度・関心が高まっていくと考えられます。
アメリカでは自己理解や他者理解などのスキルを向上させることで非認知能力を向上させるSELプログラムが実施されていますし、文部科学省でもこのプログラムにもとづいた「探究学習(自ら問いを立て、それに対して答えていく学習)」を推進しています。
非認知能力が注目された大きなきっかけは、シカゴ大学のジェームズ・ヘックマン教授が1960年代に行なった「ペリー就学前プロジェクト」という研究です。
この研究では、経済的に恵まれない環境にいる3〜4歳の子どもを集めてグループを2つに分け、片方のグループにのみ非認知能力を高める教育を行いました。
そして40年にわたって調査を続けたところ、それぞれのグループの子どもたちには認知能力に大きな違いがないにも関わらず、非認知能力の教育を受けたグループの子ども達の方が、学習成績や学歴、大人になってからの収入、持ち家率などが高く、生活保護受給率や犯罪率が低いという結果が出たそうです。
このことからも、充実した豊かな人生を実現させるためには、学力アップに偏った教育を受けさせるよりも、非認知能力の育成も取り入れたバランスを考えた教育が非常に重要であるといえるでしょう。
また、これから世界はAI時代に突入します。
その中で、計算・知識・情報・論理的説明といった認知能力にもとづくスキルの多くは、残念ながらAIに取って代わられることになるでしょう。
一方で非認知能力は違います。
非認知能力はAIが代替することはできない、人間ならではの能力、人間らしい能力と言えるでしょう。
今までの常識や価値観が通用しなくなるAI時代になったとしても、今まで以上に周りから高く評価され、思う存分に活躍するためには、非認知能力が欠かせないスキルとなることは間違いないでしょう。
AI時代を生きる子どもに必要なスキルについては「AI時代に活躍するために!子どもに必要な教育や親の見守り方とは?」もご一読ください。
非認知能力を鍛える方法は?
ここからは、非認知能力を具体的に鍛える方法をご紹介しましょう。
意欲・関心・創造性・好奇心
大人でも旅行などで新しい場所や新しいモノを見聞きすることは五感を刺激されワクワクするものです。
まして大人よりも圧倒的に経験値が少ない子どもであればなおさらです。
なにも旅行に限ったことではなく、はじめての山・川・森・海・動物・植物・音楽・美術・芸術・芸能・乗り物・施設・建物・食べ物・言語・文化・遺産などなど。
そうしたものを自分の目で見て、耳で聞いて、鼻で嗅いで、味わって、触ってみて、まさに五感をフル稼働させて感じ取るのです。
体験したすべてが好きなもの、楽しいものではないでしょう。
中には嫌いなもの、苦手なものもあるはずです。
そうしたことも実際に体験できたからこそわかることで、何が好きで何に興味・関心があるかは体験してみないと誰にもわかりません。
そういった体験を経て、自分のことも自分で理解できるようになってくるのです。
また、生き物を育てたり、料理やお菓子を作ったり、プラモデルや模型を作ったりすることも立派な体験です。
コミュニケーション・共感力・社会性
自分が思っていること・考えていることを他の人に正確に伝えること、逆に他の人が言っていることを正確に理解することは、案外、大人でも難しいスキルです。
こうしたスキルは体験して練習することでしか身につくことはできません。
つまり、練習すれば必ず上達するし、練習しなければ決して身につきません。
また、練習には相手が必要ですが、練習なので失敗しても大丈夫な相手が望ましいです。
そういう意味で練習相手に最も適しているのはズバリ、家族ではないでしょうか。
最初は簡単な意思疎通から始めて、お互いの主張を聞いたり、説得したり、反論したり、自分の気持ちや想いを伝えたりと、とにかく途中で投げ出さずに最後まで話し合うことで決着を図りましょう。
慣れるまでは話の中身・決着よりも、途中でさえぎらずに最後まで話をしたり、聴いたりすることが重要で、口論となりそれ以降、会話しなくなるというのでは練習になりませんので注意が必要です。
そうした体験を通して、自分の意見が正しいとは限らない、見方や立場によって意見が変わることもある、人によって意見や思い・考えは違うということを学び、その上で相手とどのように折り合いをつけていくのかを身につけていくのです。
自制心
子どもだからといって家庭内で何の役割も与えずに自由に過ごさせるというのではなく、家族それぞれの役割を決めて、お互いが気持ちよく過ごせるようルールを話し合って決めましょう。
犬の散歩をする、部屋の掃除をする、何時に起きる、何時に寝るといった役割やルールをお互いに納得して決めることです。
もちろん、子供の成長とともにその都度、話し合って変更してかまいません。
厳しい規則で拘束したり、コントロールしたりすることが目的ではなく、自分で決めた役割やルールを守るという経験から自制心・責任感といったものが育っていくのです。
また、起床、就寝、勉強、趣味遊びゲーム、運動など、一日の生活行動スケジュールを決めて規則正しいリズムを習慣化することも非常に有効です。決めたことは書き出して常に見えるようにしておくことが上手くいくコツです。
やり抜く力
困難なことがあっても最後まで目標目指してやり遂げるという力は、他者ではなく自分との戦い、競争に打ち勝つということです。
そのためには何事も自分で決めるというプロセスを踏むことが重要です。
子どもが小さい頃は親が選んで与えることが多いかと思いますが、なるべく早い時期から子ども自身が自分で決める、自分で選ぶという体験を積ませてあげましょう。
慣れないうちは親が選択肢を与えて最後は子どもが選ぶというのでも構いません。
年齢とともに決める事柄もスケールアップさせていきましょう。
子どもが決める際に大事なポイントは、どうしてそれに決めたのか、理由をしっかりと聞くことです。
そして、決めたからには最後までやり遂げるという責任が伴うということも必ず言い聞かせましょう。
ただし、最初から完璧を求めすぎて失敗を許さない環境を作ってしまうと逆効果になるので注意が必要です。
非認知能力を高めるために親ができるサポート・注意点
非認知能力を高めるために、親にできるサポートと気をつけるべき対応についても確認していきましょう。
親にやってほしいサポートと注意点
子どもの非認知能力の育成にあたって、次の点を意識するようにしましょう。
非認知能力は教えてできるものではない
非認知能力は学力と違って、暗記して伸びるものではありません。
だからといって難しく捉える必要はなく、家庭内における日常生活の中だからこそ、しっかり伸ばすことができるスキルということを覚えておきましょう。
五感を刺激する初めての実体験を多く与えてほしい
ワクワクする楽しい体験というとディズニーランドやUSJなどが頭に浮かぶ方も多いかもしれません。
しかし、ここで言う体験は子どもの非認知能力を伸ばす目的で考えていただきたいので、行き慣れた楽しいところというよりは、なるべく初体験を数多くできるように、毎回さまざまな場所に連れて行ってあげてください。
お金をかけて遠出する必要はありませんので、初めて見るもの、初めて聴くもの、初めて触れるもの、初めて嗅ぐもの、初めて食べるものというように、自然や施設、芸術、文化など意識をしてこなかっただけで、気づけば身近にたくさんあります。
どこに行こうか、何をしようかと考えるときに「初めて」をキーワードに探すと簡単に候補がいくつでも出てくるはずです。
親も子どもと一緒に非認知能力を伸ばそう
非認知能力は心身ともに豊かな人生を生きていくために欠かせないスキルですが、子どもだけではなく大人であっても鍛えることは十分に可能です。
ですから、子どもの非認知能力だけを鍛えよう、伸ばそうと考えるのではなく、親も一緒になって伸ばそうと考えてほしいのです。
先述の通り、非認知能力は勉強のように覚えて身につくものではなく、実体験を通して学び、気づき、思い、感じることで伸びていくものです。
勉強と違い、そこには絶対的な正解は存在しません。
また、必要な体験は子ども一人ではできません。
どこかに行かせる場合も、コミュニケーションや社会性を鍛える場合も、自制心ややり抜く力を鍛える場合も必ず相手(親)の関わりが必要となります。
親が子どもに対して一方的に相手する、教えるというものでない以上、子どもに付き合ってあげるという消極的な捉え方ではなく、せっかくだから自分も子どもと一緒に非認知能力を鍛えようと前向きに捉えて、一緒に楽しみながら取り組んでいただきたいと思います。
「宿題やったの?」と言っているうちはダメ
非認知能力を意識している親は、絶対にこのようなことを子どもに言いません。
なぜなら、これは意欲や自制心、やり抜く力といったものを減退させるからです。
つまり、言えば言うほど逆効果ということを親がわかっているからです。
では、親は黙ってすべてを本人任せにして放任すればよいのか、ということでもありません。
事前に本人とちゃんと話し合って、役割やルール、目標といったことを決めています。
それを決めた上で、親は見守っているのです。
決して子どもをコントロールしない、支配しない、強制しない、甘やかさないのです。
もちろん、これは子どもの学年によって関わる程度に差が出ますが、できる限り本人に考えさせて、決めさせるようにして、親はできた結果よりも非認知能力の成長部分に注目して褒めてあげてください。
完璧を求めない、完璧を目指さない
非認知能力を鍛えようと一生懸命になり過ぎてしまい、何事も完璧にできるよう子どもに求めたりする親御さんがいらっしゃいますが、これは逆効果になるので絶対にやめてください。
非認知能力は失敗しない能力ではないし、完璧にこなす能力でもありません。
むしろ逆で、失敗したり壁にぶつかったりしても、諦めずに最後までやり遂げる能力を鍛えることなので、失敗していいんだ、失敗は怖くないんだという環境を用意してあげることが親に求められます。
完璧を求めてしまうと、失敗したらどうしようと不安のほうが大きくなり、その結果として挑戦しなくなる、意欲・関心がなくなる、言われた通りのことしかやらない、上手くいかないとすぐに諦めるという非認知能力がない状態へと子どもを導いてしまいかねませんので注意が必要です。
親の失敗談は最高の教科書
最初から失敗しない人はいません。
非認知能力においても同様で、失敗しながら、壁にぶつかりながら、大きく成長していくものです。
失敗しても次にどうやってそれを乗り越えて立ち直り、ゴールを目指すのかということを体験から学ぶのです。
失敗は決してダメなものではなく、次の成長につながる糧となるということを、親が自身の失敗談を例にして子どもに話してあげると良いでしょう。
みんなさまざまな失敗を経験して成長しているということを子どもが理解できれば、失敗を恐れずに挑戦しようとする気持ちが育つことでしょう。
子どもに自分の失敗談を話しても、子どもは決して親を馬鹿にすることはなく、むしろ人生の先輩として尊敬してくれるので、どんどん聞かせてあげてください。
非認知能力の教育に適しているマンツーマン指導
現在の一般的な塾や学校では、学力を身につけさせる認知能力の教育を主に行っています。
しかし、ご紹介したように、子ども達にとって重要なのは認知能力だけではなく、非認知能力の教育が今後、ますます求められるようになるでしょう。
認知能力は学校の一斉授業で効率的に教育することが可能ですが、非認知能力は点数化できず評価しにくいことや、個人別の対応が求められるために集団型の授業では難しいといわれてきました。
家庭教師のファミリーでは、「学力だけでなく人間力を育てる!」をコンセプトに、創業以来22年間、マンツーマン指導だからこそできる非認知能力の育成に取り組んできました。
子どもの成績が良くないから、もっと勉強をして学力を伸ばしたいと希望される保護者様は大勢いらっしゃいますが、ほとんどの方は「教え方が上手い先生が教えれば成績が伸びる」と勘違いされています。
成績が伸びない主な理由として、普段から勉強していないということは間違いないのですが、勉強しない理由の大部分が非認知能力の未発達・不足にあるという点をご存じない方が大勢いらっしゃいます。
実際に、週に4日・5日と毎日のように塾通いしているのに、思うように成績が伸びないというご相談をいただきますが、子どもの非認知能力に問題がある場合は、その非認知能力を鍛えないかぎり、悩みは解決しないのではないでしょうか。
家庭教師のファミリーでは、学力を伸ばすためにはその土台ともいうべき、非認知能力の育成が最重要と捉えており、特に学力アップに影響する項目を「自立学習力」と定義しています。
これらをわかりやすく数値化することで、「学力」と「自立学習力」の相関関係がはっきりと理解され、子どもの学力問題の解決に大いに役立っています。
勉強を教えることは集団でも個別でもできますが、その子の特性や行動習慣・思考習慣に併せて、今その子に必要な自立学習力の指導というものは、1対1のマンツーマンスタイルが最も適しているのかもしれません。
非認知能力は「心身ともに充実した人生」を生きていくために欠かせない能力
認知能力は学習テストやIQのような数値化できる知的能力、非認知能力は思い・考え・気持ちなど内面的な能力を指す言葉です。
非認知能力には、自己肯定感、主体性・意欲、物事をやり抜く力、創造性、好奇心、自制心(セルフコントロール)、共感力、コミュニケーション力、社会性などが挙げられます。
非認知能力を高めることは、人生の豊かさに影響することが報告されており、またAIに代替できない能力でもあることから、近年重要視されています。
また、学力を伸ばすためにも、実は非認知能力が大きく関わっており、非認知能力を鍛え、伸ばしていくことが結果的に学力アップにつながるといわれています。
非認知能力は学力などの認知能力と違って、暗記して伸びるものではありません。
日常生活のさまざまな体験を通して失敗しながらも気づき、思い、感じることで身についていくものなので、一番身近な親の存在は良くも悪くも子どもの非認知能力に多大な影響を与えることを知っておきましょう。
子どもが勉強しない理由が主に非認知能力にあるという場合は、認知能力(学力)を伸ばす学習塾に通わせることが、実は問題解決に直結しないということがご理解いただけたのではないでしょうか。
家庭教師のファミリーでは、保護者の皆様に非認知能力の重要性を理解していただき、また、日常生活の中で実践していただくよう働きかけています。
同時に子ども達に対しては、自立学習力の診断結果を基に非認知能力の育成に力を入れながら教科指導も行い、結果的に学力アップへと導いています。
塾や通信教育など、いろいろ勉強をさせているはずなのに思うように成績が伸びないという方や、子どもの非認知能力に興味・関心があるという方は、お気軽に家庭教師のファミリーにご相談ください。
相談は無料で行っており、オンラインでもお受けしております。
また、自立学習力診断もオンラインで無料でご利用いただけますので、お子様の自立学習力を知りたいという方はご活用ください。
著者ファミリー 代表 寺井俊行

大学生の家庭教師が主流の中、顧客からのより専門的で高度な要求に応えるため、教師のプロフェッショナルとして、質の高い授業を提供。
常にハイレベルな授業を提供できるように、日々指導法や教材の研究等を行い、また、大学生や一般の家庭教師に対して研修や授業のアドバイスを行うことで、ファミリー全体の授業スキルの向上を図っています。
お電話でのお問合せ
フリーダイヤル

14:00〜21:00
(日祝休み)
- 教育情報コラム
- 先輩たちの成功体験談
- ファミリーの賢い利用法
- 勉強お役立ち資料
お電話でのお問合せ
フリーダイヤル

14:00〜21:00
(日祝休み)