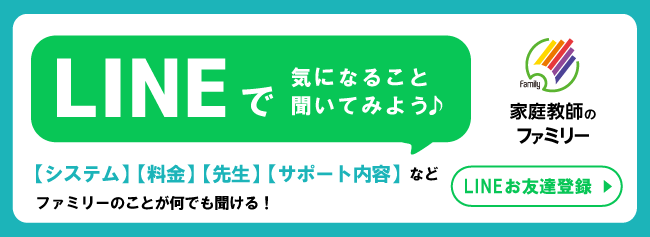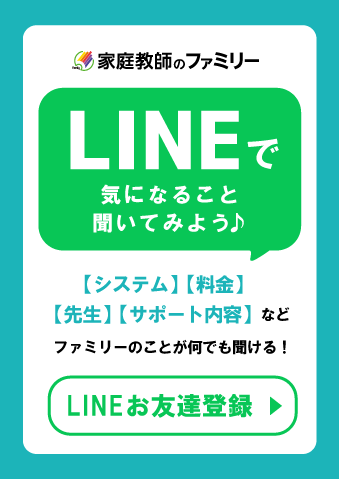定期テストは計画立てが大切!学習計画や期間ごとの対策法
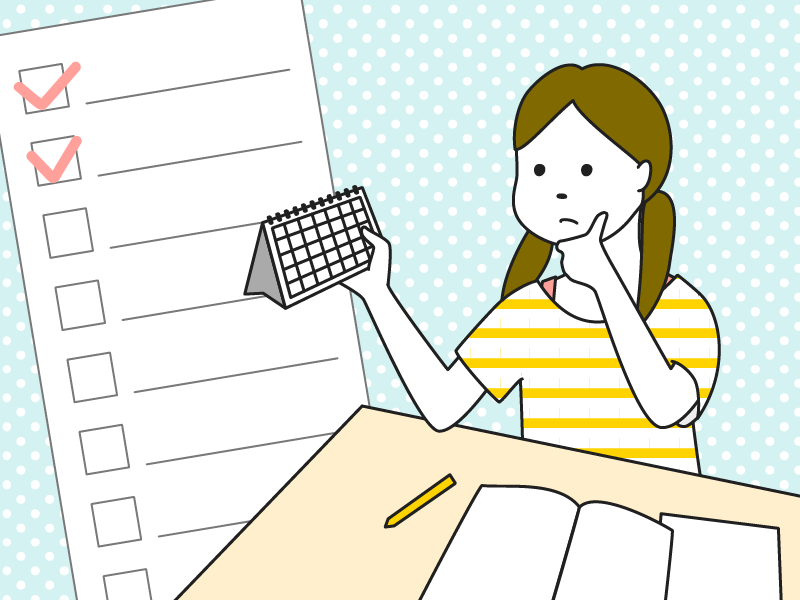
2021.05.17
木戸 貴之
こんにちは! 家庭教師のファミリー認定プロ教師の木戸です。
定期テストの勉強って、「いつから」「なにから」「どのように」始めればいいんだろう・・・とお悩みのお子さまは案外たくさんいます。
初めから要領よく出来る子は少ないですから、早め早めの対策が必要です。
どの時期からどんな対策をすべきか、科目毎にポイントを確認していきましょう!
定期テストで重要な学習ポイントをもとに計画を立てよう!
定期テストは「これまでに勉強したことが、身についているかどうか」を確認するためのものなので、習っていない単元から出題されることはありません。
「学校で勉強したこと」が出題されるということから、次のような学習ポイントがあげられます。
それらを参考に、定期テスト当日までの計画を練っていきましょう!
副教材とノートが定期テストの重要ポイントに!
多くの中学校で教科書の他に「副教材」を使用しており、地域差や科目差はありますが、これらの教材から相当数の出題が見られます。
また、テスト当日に副教材やノートの提出が多く見られることから、副教材とノートを使った勉強はとても重要といえます。
「副教材の問題なら大丈夫!」という状態にすることも大事ですが、なぜ答えがそうなるのかを説明できる状態にすることが重要です。
副教材の模範解答は、暗記のためのものではなく、根拠を明確にするために使ってみましょう。
復習がメイン!ニガテ科目は前学年の見直しも必要
何度も言いますが「これまでに学習した内容」が出題されるため、勉強は復習が中心になります。
特に、学期初めに習った内容は、時間が経っていて忘れていることが多くあるため、この単元から復習をすることが、テスト対策の基本となります。
中2生や中3生の場合、前学年のニガテ単元を引きずってしまうことも少なくありません。
特に、英語と数学はその単元の基礎をそれ以前の学年で習うことが多いため、理解が不十分の場合は前学年のニガテを解決しなければ、現学年の内容を理解することは難しいです。
もし練習問題や副教材の問題でつまづいてしまったら、場合によっては、前学年の教科書や副教材を見直すだけでなく、解き直す必要があることも頭に入れておきましょう。
演習が大事!理解するだけでは得点にならない
知識や解き方を、教科書や副教材を通じて頭にインプットしたらもう大丈夫!
ではありません。残念ながら。
理解したからといって、果たしてそれがすぐできるようになるでしょうか?そうではない経験を日常生活の中でも様々な形で経験してきているはずです。勉強も同じ。
頭に入れたことは使ってみないと、使えるものかどうかはわかりません。だからたくさん演習をして実践経験を積むのです。
それが積みあがってくると、ようやく「できる」状態になります。できる経験を増やして、自信を持ってテストを受けましょう。
定期テストまでのスケジュール!1ヵ月前からの学習計画を参考に

定期テスト対策のポイントは、毎日少しずつ行うことなので、1ヶ月前からはじめるのが理想です。継続は力なり!です。
では、具体的にどのようなことをすればいいのか見ていきましょう。
定期テスト4~3週前
◆メインは副教材!忘れていることを思い出そう
この時期は、「忘れていることを思い出す期間」として、とても重要です。直前に対策を始めても、調べている余裕がほとんどないためです。
この忘れていることを思い出すのに最適なのが「副教材」です。
副教材の問題を通して忘れていることを確認し、教科書やノートに赤ペンなどで印をつけておくことで、直前に見直す際の準備を整えておくことができます。
一教科15~20分程度のゆっくりとしたペースでも全ての範囲を拾えるはずですから、早い段階で手をつけておきましょう。
テストまでに何周も解けるようにするため、副教材には直接答えを書き込まずに、ノートなどに書くことをオススメします。
同じ間違いを繰り返したり、一度正解した問題を次に間違えるということは、きちんと理解が出来ていないということ。
それに気付くためにも、繰り返し解くことは王道ですが、効果的な勉強方法です。
◆学校ノートは定期テストの出題範囲そのもの
また、ノートは早いうちに整理しておきましょう。ノートには、先生が授業で言った大事なことが書かれていたり、重要な語句に何度も線が引いてあったりするため、テスト対策には欠かせない教材の一つです。
友人やクラスメイトとノートを見比べてみて、お互いに書き忘れていることを教え合い、自分なりの完璧なノートを作ってみましょう。
定期テスト2週前
◆内申点アップに重要!副教科対策も忘れずに
この時期から副教科の勉強にも手を付け始めましょう。
多くの学校で、副教科においても副教材の提出を求める先生が多いため、早めに提出の準備をして、時間と気持ちに余裕を持っておきましょう。
提出範囲のページ数が少なく余裕があるようなら、ノートなどを使って反復練習をするとさらに効果的です。
◆ニガテの確認と理解度をチェック!
5科目については、この時期に副教材の2周目の演習に入るのが理想です。
一度解いている問題ですから「同じ間違いを繰り返している問題」や「前回は正解したのに今回間違えた問題」に注目し、間違えた原因をしっかりと究明することが大切です。
また、問題を解くのにかかった時間を確認することも重要で、2回目であれば、普通1回目よりも早くキーワードが目についたり、答えが浮かんだりするものです。
前回より時間がかかっているような場合は、解き方が身についていないか理解度が低い可能性があるため、似た問題を通して、語句を理解し直すことや解き方を整理することが必要になるでしょう。
また新しい知識が多くなる理科・社会に関しては、別教材での演習を始めると尚よいです。
定期テスト1週前
◆様々な問題に触れ、応用力アップ!
数学や英語は、副教材の勉強と並行して過去問に取り組むなど、「多くの問題に触れる」時期です。
様々なパターンの問題を通して理解度を深め、応用問題に対応できるようにしましょう。
また、過去問には答えがついていませんので、正解がわからない問題は担当の先生に聞くなどして、正しい答えや解説をメモしておくことも重要です。
より多くの問題に触れる時間を確保するためにも、副教材はできるだけ早く終わらせましょう。
時間に余裕を持つということは、直前になって提出範囲が変更になった場合にも焦らず対応することができるというメリットもあります。
◆思い違いを見直すラストチャンス!
公式を逆に覚えていた、単語の意味を誤解していた…などの思い違いは、直前になって気づいても、なかなかすぐに直せるものではありません。
この時期が思い違いを直す最後の機会になるので、過去問や副教材その他教科書の問題などを通して、丁寧に確認してください。
そして重要なのは確認にとどめず、演習することですね。
定期テスト3日前
◆模擬練習は解答時間の短縮が鍵!飛ばす勇気も必要
ここまできたら、本番当日と同じように制限時間内で過去問などをとにかく解く「模擬練習」をやってみましょう。
時間を意識することで緊張感が生まれ、いつもより解くのに時間がかかるかもしれません。
もし時間が足りなければ、どこかの時間を削らなければいけませんから、どこに時間がかかったかを認識することが大切です。
例えば、
①考え込んで手が止まっている時間はないか?
②解きながら迷っている時間が長くないか?
③解けなかった問題に時間を費やしていないか?などです。
①と③の場合は、問題を「飛ばす」勇気も必要です。すぐにスラスラと解けない問題に時間を使うよりも、飛ばして解ける問題から手を付けた方が効率的ですし、すでに解いた問題の見直しをした方が得点になる場合もあります。
限られた時間の中でいかに、「ペンを止めずに動かしていられるか」を考えることがより多くの点数を取るための近道であり、この体験を3日前にしておくことで、本番での気の持ち方が格段に変わります。
②の原因として、問題を解く過程の理解度やキーワードの整理が不十分なことが挙げられます。
そのため、今一度その問題に関する解説などを見直し、少しでも不安がなくなるように理解を深めることが必要です。
◆「解けない」「わからない」ことを認めよう
この時期に「解けない問題」が出てきた場合、最後まで頑張ってその問題にチャレンジしようとすることも大切ですが、わからないことを認めることも同じくらい大切です。
真剣に頑張っていても解けない問題はどうしてもでてきてしまうものです。
これを認めることで、①や③のようなケースでの時間の浪費を防ぐことができ、限られた時間を有効に使えるようになるでしょう。
計画が大事な定期テスト!余裕を持って早めの取り組みを
ここまで、1ヶ月前からの勉強方法を詳しく書いてきましたが、勉強のスピードは一人一人違います。
大事なのは1ヶ月前からテスト勉強を始めることではなく、余裕を持って計画を立てて勉強するということです。
早めに始めていれば、それだけ時間的にも気持ち的にもゆとりが生まれます。
テスト前に焦って勉強をしても気持ちばかりで頭がついていかない…というのはよく聞く話です。
後悔しないように、早めの対策を心掛けましょう。
苦手単元の復習は長期連休がチャンス!
家庭教師のファミリー期別講習・特別講習では定期テストや入試で重要となる単元を厳選したレクチャーなど、確実に身につくプログラムをご用意しています。
ぜひお気軽にお問い合わせください!
著者木戸 貴之

長年にわたり塾講師など教育に携わっており、これまでに指導してきた生徒は500名以上。生徒一人ひとりに合わせた指導で、難関校にも多数の合格者を輩出している。受験に関する膨大な知識が頭の中にインプットされているとか…
お電話でのお問合せ
フリーダイヤル

14:00〜21:00
(日祝休み)
- 教育情報コラム
- 先輩たちの成功体験談
- ファミリーの賢い利用法
- 勉強お役立ち資料
お電話でのお問合せ
フリーダイヤル

14:00〜21:00
(日祝休み)